🐋 ホエールスイムのルール、年々厳しくなってない?
― 現場から見た“変化”と、ちょっとした違和感 ―

はじめに
ホエールスイムを始めてから、もう何年かが経った。
シーズンには奄美の海に通い続け、クジラたちと出会い
あの瞬間にしかない“感動と共存”を感じることが何度もあった。
でも――最近、**少しずつ「何かが変わってきてる」**と感じている。
年々、ルールが増えていく。
スイムの回数が制限されたり、ガイドが先に入り後からガイドの所に泳いでくスタイルになったり、
水中では“止まって静かにじーと”という指示が強くなったり。
もちろん、クジラへの配慮は大前提。
それを忘れていいとは思っていないし、クジラが嫌がるような接し方はしたくない。
でも、その一方で、ふと疑問が浮かぶ。
「今のルール、本当に“クジラのため”なんだろうか?」
「誰が、どこを見て決めているんだろう?」
🐳 ルールは本当に“個体”を見ている?
クジラにもいろんな性格がある。
近づいてくる個体もいれば、距離を取りたがるクジラも。
中には「人間と遊ぶのが明らかに好きそうな親子」だって、確かにいる。
でも今のルールは、すべての親子クジラを同じ扱いにしている
静かに、短く、離れて、2回まで。
それが本当に“その親子”にとって最適な距離感なんだろうか?
例えば、「2回しか入れない」ルールがあるからこそ、逆に船長たちは慎重にならざるを得ない。
「このタイミングで本当に入って大丈夫か?」
「あと1回しかチャンスがない…」
そう思えば、当然判断は慎重になる。
そして結果、どうなるかというと――
船は長時間、親子のそばで“タイミング待ち”をするようになる。
動きを見張り、浮上のリズムを読み、少しでもいいタイミングでエントリーさせられる瞬間を探し続ける。
でもそれって、
「エントリーするより、見張られる時間が長い」という状態になる。
数年前は制限がなかった。
だからこそ、現場ではもっと柔軟な判断がされていた。
入ってすぐ反応が悪ければ、船長が「嫌がってますね。次行きましょう」と即判断し、
スムーズに切り替えて、クジラにも負担をかけずに済んでいた。
でも、**今は「2回までしか入れない」**という縛りがある。
だから船長もスイマーも、1回1回を重く考えざるを得なくなってしまった。
「今入るべきか?」「このタイミングは大丈夫か?」
とにかく慎重になり、一瞬の判断がしづらくなる。
それ、本当にクジラにとってストレス少ないのか?

その結果――
クジラのそばで長時間様子をうかがう“張り付き”が増え
判断に迷って動けない時間が長くなることで、
クジラにとっては逆にプレッシャーが大きくなっている可能性もある。
本来であれば“サクッと入って、サクッと離れる”というスイムスタイルだったのに
今は「入るまでが長い」「入ったら失敗したくない」の心理的プレッシャーだらけになってしまっている。
そして、こういった“ルール優先”の流れは、
現場の判断力にも影響を与えはじめている。
「2回しかない」
「絶対に成功させたい」
そういう思いが強くなればなるほど、
スイマーも船長も、クジラを思う気持ちをどこかに置いてきてしまっている
本来なら「今日はこの子、やめとこう」「この動きはやめよう」といった柔軟な判断ができたはずなのに、
今はその判断が、焦りや欲で鈍ってしまうこともある。
むしろ、「1回の人数を8人から4人に減らす」方が、クジラから見える人数も少なく圧のプレッシャーは少ないのでは?
サクッと入って、ダメそうならすぐに切り上げる。
無理に粘らず、必要以上に船で追わない。
それができれば、
クジラにも、スイムする側にも、そして周りの船にも優しい流れが生まれる。
一隻が長く居座れば、他の船も集まりはじめる。
そしていつの間にか、じっと見つめるだけの大集団”になってしまう。
そうなると、親子クジラの“ご機嫌”がよくなるはずもない。
🔊 音への配慮の不思

フィンの音はダメ。
でもスクリュー音はなぜか許される。
実際に水中で聞いた人なら分かると思うけど、
フィンの音よりスクリュー音の方がよっぽど響いてる。
でもフィンバシャバシャが目立つから、スイム側に都合よく「配慮しろ」と言われる。
それって、本当に生きものへの配慮なのか?
“人間社会向けのアピール”になっていないか?
もちろん泳ぎ方はスマートではないし音を立てて向かえば人が来た、追われている
と感じさせてしまう。フィンを沈めて向かう、それは大前提
だけど他船が近づいてくるスクリュー音のがよっぽど威圧的だ。
そんな違和感も、正直ある
🧭 「スイムじゃなくて、もうウォッチングじゃん?」
最近では、ショップ側も「スイムとは言えない」と苦笑しながら、
「水中ウォッチング」という言葉を使うことも増えてきた。
僕はスイムそのものにこだわっているわけじゃない。
でも、クジラの反応に合わせて「どう近づくか」を考えるのも、
“泳ぐ側の責任”と“楽しさ”の一部だったはず。
すべてをガイド任せにして、「ただ付いていくだけ」になるのは、
全体の質も悪くなりクジラへの向き合い方を考える力を低下させている
何か大事なものを置き去りにしてる気がしてならない
🐋 最後に:僕はただ、ちゃんと向き合いたい
クジラを守ること。
海に感謝すること。
ルールを守ること。
どれも大切なことだと思う。
でも、その前に一つ大切なのは、
“ちゃんと目の前のクジラを見ているか”ということ。
ルールをつくる人たちも、現場に来て、実際にその場の空気を感じてみてほしい。
見る目や向き合う姿勢が育たなくなる。
一律じゃない“命のかたち”が、そこにはあるだからこそ
クジラとちゃんと向き合って泳ぐことが必要
その姿勢があったからこそ現場ではもっと柔軟な判断がされていた。
水中ではどんな動きだったかを船長と話、反応が悪ければ、船長が「嫌がってますね。次行きましょう」と即判断
スムーズに切り替えて、クジラにも負担をかけずに済んでいた。
今は「2回」来期はおそらく「1回」という縛りになる。
ルールが厳しくなると人は考えなくなる
「ルール通りにやっているからOK」そして自分の行動に責任を持たなくなる
クジラをただの対象物としてみてしまう
「撮れるかどうか」「入れるかどうか」見えたかどうか
必要なのは一頭一頭に対する考え方、感じ方。
ルールが厳しくなればなるだけ一瞬の判断がしづらくなる。

🐋 もっと知りたい方へ…
▶︎ [ザトウクジラについて詳しく見る]
▶︎ [ホエールウォッチング・ホエールスイム体験はこちら]
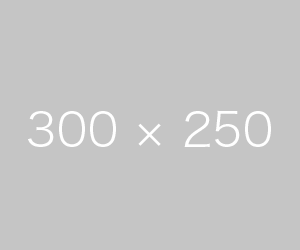
コメント